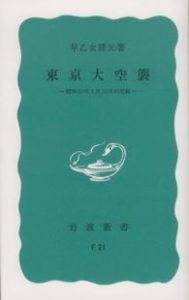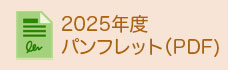理事推薦本
早乙女 勝元 著、『東京大空襲ー昭和20年3月10日の記録』(岩波新書 1971)
私がこの本に出会ったのは、高校3年生の時である。日本史の先生が「定期テストの追試の代わりにこの東京大空襲を読んでレポートすれば単位を認定する。」と話されたのだ。何十年ぶりかで読み返してみたが、著者の取材の根気強さ、描写の生々しさに圧倒された。そして罹災の信じられない規模とむごさに。
筆者自身の体験と空襲体験者への聞き取り調査による証言がドキュメンタリー風の記述で「東京大空襲」が語られている。昭和42年江東区の地下鉄工事現場で、防空壕跡らしきものが発見され、中に6体の人骨があった、ということから書き起こされている。
東京大空襲 1945年3月10日0時15分空襲警報発令ー2時37分まで(142分間)
死者 8万8793人 (10万人余りともいわれている)傷者4万918人
対象 東京下町(浅草区、深川区、本所区、城東区など)
アメリカ軍B29爆撃機(150機)による
「勝元、起きろ!」父の声に、私ははね起きた。南の窓ガラス越しに、目もくらむばかりの光線がつきささる。そしてドカドカと地脈をゆするような不気味なひびきが、とどろきが。――ここから著者の3月10日東京大空襲がはじまる。筆者だけではなく、前日までときおり空襲があるとはいえ、ささやかな暮らしを営んでいた下町の一般市民は今までに経験したことのない激しい空襲にさらされたのである。米軍機は単独あるいは数機ずつに分散して低空から波状絨緞爆撃を行ったため、多数の火事が発生し、烈風により合流火災となり、東京の4割を焼き、甚大な被害を生じた。
都民の虚を突いて来襲したB29の大編隊は火災を爆撃目標に周囲に巨大な火の壁を作り、逃げまどう人びとに狙いを定めて、人家のすれすれまで高度を落としての集中攻撃をした。
風速2,30メートルの強風は、深川、本所、城東地区を中心につぎつぎと発生した火災を合流させ、火の海の沸騰となって、下町そのものを、巨大な炎のるつぼにかえてしまった。大火流、吹きつける熱風、空からは焼夷弾の束が無数に投下される中を逃げ惑う下町の人びと、地獄絵図であった。火の壁に囲まれた人びとは活路を見いだそうと水のあるところ運河を目指す。しかし、橋に殺到した人は追って来る炎に水に飛び込む。小舟やイカダに助けられた人もいたが、多くの人が運河に沈んだ。背中に子どもを背負った母親が一息ついたとき、我が子が息絶えていること知るということもあった。
またこの空襲を記録したカメラマンは、猛火渦巻き狂う修羅場とともに、倒れている焼死体、母子の死体、死体の山に、シャッターボタンを心を鬼にして押したと証言している。
午前5時10分、猛火は鎮火に向かい、朝がきた。塵芥と化した町では隅田川の岸壁で警防団が、水中のおびただしい焼死体、水死体を引き上げていた。親を失った子ども、子を失った親、引き裂かれた妻と夫……
これ以後も大阪をはじめ日本各地は、アメリカの空襲をうけた。終戦の8月15日の熊谷空襲まで。
被災者の数は原爆の広島、長崎に匹敵するほどのものであるにもかかわらず、国の補償を何ら受けていない。軍人、軍属とちがって「一般国民は戦争の被害を甘受すべき」という理由によって。
第二次世界大戦以後、戦争は戦闘員だけではなく非戦闘員も巻き込んだものになり、多くの犠牲者を生んできた。今、世界ではウクライナでガザで、80年前の日本と同じ戦争による惨禍が起きている。
今年は戦後80年である。戦後ではなく戦前としないために、私が高校の先生から受け取った「戦争をしない、させない」という意志を、この本を紹介することにより皆さまにも伝えたい。(KM)