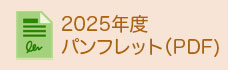若手教員の学校での悩みと課題の社会構造との関連を検討する
授業研究会では、2024年に引き続き、若手教員の学校での悩みを語ってもらうことを出発点としつつも、2025年度は、さらに踏み込んで、それらの課題が社会構造とどのように関係しているのかを検討していく方向で、議論を深めていきたいと考えています。特に焦点をあてるのは、以下の2点です。
①東京一極集中を促してきた高度経済成長の背後には資本主義という社会構造があるわけですが、それが教育をどのように縛り、私たちの価値観に入り込んでいるのかという点。
②2024年度に引き続き、「フル・インクルージョン」に向けた実践の阻害要因を検討するという点。
各回の構成は、若手教員を中心とする現場報告を中心にする場合と、論文検討や講演を中心に進める場合を組み合わせて進めていきます。
教室の実践を、子どもと教師の人間関係に閉じ込めず、より広い視野から検討できるようにするため、子どもを観察する観点を幅広く獲得すると同時に、観察の結果を社会構造と結びつけて検討できる幅広い知識の獲得を目指します。
開催日時(全6回・原則対面(5~12月は理論学習会の後の時間)
①3月29日(土)16:15~18:15 論文検討:卒業論文「脱資本主義の思想としての地方移住の可能性を考える-教育観や子育てに対する考え方に焦点を当てて-」の検討
②5月17日(土)16:15~18:15 現場からの報告による検討
③6月14日(土)16:15~18:15 講演と質疑:講演「授業を通してみる子ども像と学校像」
④8月30日(土)16:15~18:15 現場からの報告による検討
⑤10月25日(土)16:15~18:15 講演と質疑:講演「生活綴方は資本主義にどう向き合ったのか」(講師:桑嶋晋平氏(日本女子大学 准教授)
⑥12月13日(土)16:15~18:15 現場からの報告による検討