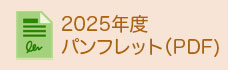「Ed.ベンチャー」は、市民や退職教員・研究者や現職教員が集まって立ち上げた社会教育団体です。目的は、目の前の子どもたちや先生、学校や保護者が直面する問題を共有し、とくに弱い立場に置かれた子どもも含め、すべての子どもや先生(学校)が明るい未来を創造するためのお手伝いをすることです。
主な活動
・学習に遅れる子どもたちの支援 ・学校が必要とする様々な支援
・外国人や弱い立場の子どもたちの支援 ・教職員とともに教育を考える活動
・市民とともに教育課題を考える活動
Ed.ベンチャー 新 行動宣言(PDF)
2026年度事業方針
昨年の年末から年始にかけて、世界では耳を疑うような出来事が繰り広げられた。それらはアメリカ(トランプ大統領)が中心となっての出来事が多い。ベネズエラへの侵攻と大統領の拘束、66の国際機関からの一方的脱退。挙句は「ドンロー主義」宣言、と続く。戦後構築されてきた国連を中心とした世界の枠組みや理念が、吹き飛びかねない状況に置かれた。こうした世界の動きを受けて、各国では今後の対応を模索中だ。
こうした報道に触れるたびに、やはり世界に戦争の足音が近寄りつつあるのではないかと、心配になる。ヨーロッパでは停止や縮小していた徴兵制を復活する動きが盛んだ。ドイツでは、18歳の男女に兵役の意思を問うとともに、男性には身体検査を義務づける法律が施行された。志願兵が不足すれば、議会の承認で徴兵制を再開するとのことだ。
こうした動きは今の子どもたちにとっても無縁ではない。子どもたちが大人になるときに、どのような社会を残してあげられるかは、現在の大人たちの責任だ。
こうした中で、教育に関わる者たちがやるべきことは何なのか、私たち一人ひとりが問われている。
昨年度の事業方針では、画一的な価値観の中に押し込められるのではなく、何を大切にしたいのかという「手作りの価値観」を確認しながらの、お互いを支え合うネットワークづくりを提唱した。
手作りの価値観とは言っても、そこには底流を流れる共通の大きな理念があるはずだ。すなわち、「自由・平等・平和」である。この「自由・平等・平和」は、人類の歴史の中で世界的に共有されているはずのものである。歴史の中で人類が獲得した価値観、と言っても過言ではない。しかし、いまそれが危ない。
であるならば、私たちが今年取り組むべきことは、学校教育にとらわれることなく、活動の様々な場面で、大人も子どもも、「自由・平等・平和」の大切さを確認し合うことではないだろうか。歴史が巻き戻されそうになっている今、「何が大事なのか」だけは常に確認しなければならないと考える。
経済の発展が私たちの幸福につながると信じてきた。しかし、経済の発展が行きつくところまで来てしまった現在では、少ないものを取り合う生き残りゲームが始まっているかに思える。強いもの、資金のある会社や個人だけが生き残る時代がやってきた。「自由・平等・平和」がそうした中で脅かされているのである。経済の発展は必ずしも「幸せ」を呼ばないこともわかり始めている。
だからこそ、私たちは「お互いの幸せを守り合う社会をイメージできる力」を子どもたちに育てていかなければならないのだ。そのイメージは、私たちの中でもまだ漠然としているが、今取り組まなければならないことだけは確かだ。
より良い未来の社会を想定しながら、私たちは学び合い、語り合い、そして成長していきたいと考える。
設立の趣旨/定款
組織
事業計画/予算
事業報告/収支計算・貸借対照表及び財産目録
2025年度 事業報告(PDF)/収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
2024年度 事業報告(PDF)/収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
2023年度 事業報告(PDF)/収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
2022年度 事業報告(PDF)/収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
2021年度 事業報告(PDF)/収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
2020年度 事業報告(PDF)/収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
2019年度 事業報告(PDF)/収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
2018年度 事業報告(PDF)/収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
2017年度 事業報告(PDF)/収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
2016年度 事業報告(PDF)/収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
2015年度 事業報告(PDF)/収支計算書・賃借対照表・財産目録(PDF)
2014年度 事業報告書(PDF)/収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
2013年度 事業報告書(PDF)/収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
2012年度 事業報告書(PDF)/一般会計 収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
すたんどばいみー基金 収支決算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
東日本大震災支援事業 会計報告・貸借対照表・財産目録(PDF)
2011年度 事業報告書(PDF)/一般会計 収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
東日本大震災支援事業 会計報告・貸借対照表・財産目録(PDF)
2010年度 事業報告書(PDF)/法人化前 収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
法人化後 収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
2009年度 事業報告書(PDF)/収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
2008年度 事業報告書(PDF)/収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
2007年度 事業報告書(PDF)/収支計算書・貸借対照表・財産目録(PDF)
沿革
2007年
9月 (非営利)教育支援グループEd.ベンチャー設立総会開催
2008年
1月 「すたんどばいみー基金の会」をEd.ベンチャー組織内に位置付け
2月 設立記念講演会開催。テーマ:「<職業>としての教育―あるいは職業としての教師」 講師:東京大学大学院教育学研究科教授 苅谷剛彦先生
4月 外国人支援活動子ども支援部「エステレージャ・ハッピー」開始
2009年
2月 教育講演会開催。テーマ:「教師であることと、市民であること」 講師:東京大学大学院教育学研究科准教授 小玉重夫先生
3月 外国人支援活動大人支援部「生活相談」において、月1回の日本語教室への出張相談を開始
4月 外国人支援活動子ども支援部「保証人事業」開始
7月 『会報』発行開始
2010年
1月 学校支援活動学校支援部「調査援助」を「研究者による支援」に改め開始
外国人支援活動子ども支援部「エステレージャ・ハッピー」から厚木教室「Kokusai B.G.」立ち上げ
外国人支援活動子ども支援部「すたんどばいみー」を外部関連協力団体として位置付け、「当事者活動支援」開始
2月 教育講演会開催。テーマ「家族と教育の関係性の変容」 講師:東京大学大学院教育学研究科教授 本田由紀先生
3月 国際教室担当マニュアル「はじめての国際教室担当」発行
6月 特定非営利活動法人として神奈川県より認証を受け、NPO法人教育支援グループEd.ベンチャーとなる
9月 緊急ホームレス支援開始、法人の外部組織として「連帯保証人グループ」立ち上げ
10月 八王子国際協会主催「外国につながる児童生徒のための学習支援ボランティア講座」に講師派遣(~12月、全6回)
12月 神奈川県立湘南養護学校の校内研修会に講師派遣
2011年
1月 外国人支援活動大人支援部「生活相談」の出張相談が月1回から毎週となる
2月 教育講演会開催。テーマ:「『貧困』の現実と『教育』~『反貧困』の活動から~」講師:活動家 湯浅 誠 氏
4月 「東日本大震災支援事業」開始、岩手県陸前高田市の学校再開・避難所支援、宮城県石巻市万石浦の子ども支援、福島県富岡町の学校再開支援を行う
「東日本大震災支援事業」において、すたんどばいみーの陸前高田市モビリア避難所子ども支援活動の後方支援開始
7月 外国人支援活動子ども支援部「保証人事業」において、「報告会」を開始、以降年2回報告会を開催
11月「東日本大震災支援事業」において、岩手県陸前高田市の現地市民団体・教育支援チーム「まつ」の支援開始
2012年
1月 学校支援活動教師・保護者支援部「授業研究会」を「小5・6教室」に改める
小学館『小四教育技術』に「東日本大震災支援事業」の記事掲載
2月 教育講演会開催。テーマ:「『親密性』と『排除』~子ども社会・子どもを取り巻く社会~」 講師:筑波大学大学院人文社会系教授 土井隆義先生
3月 『東日本大震災支援活動報告書』発行
4月 「東日本大震災支援事業」万石浦子ども支援を学生主体に立ち上げた「ライオン学校」が引き継ぎ、以降法人が後方支援を行う
8月 「東日本大震災支援事業」において、神戸定住外国人支援センターと共催で「ライオン学校伊豆学習旅行」開催
陸前高田市立小友中学校・大和市立下福田中学校・すたんどばいみー共催の三者交流会を支援
11月 神奈川新聞「心豊かな街へ」欄に当法人紹介記事掲載
12月 神奈川新聞社・神奈川新聞厚生文化事業団より第25回神奈川地域社会事業賞受賞
2013年
1月 『小友中学校×すたんどばいみー×下福田中学校 交流会報告書』発行
学校支援活動教師・保護者支援部「小5・6教室」を「授業研究会(小5・6)」教室に改める
「エステレージャ・ハッピー」「Kokusai B.G.」を外国人支援活動子ども支援部「子どもの居場所・学習教室」として位置づけ
2月 教育講演会開催。テーマ:「つなぐ力・のりこえる力・・・被災地の実践から、教育の可能性を学ぶ」 講師:岩手県陸前高田市立小友中学校校長 加藤 清 先生、福島県南相馬市立原町第一小学校教諭・日本作文の会副会長 白木次男先生
5月 「子どもの居場所・学習教室」「お父さんとお母さんのための日本語教室」「生活相談」を県中央地域労働者福祉協議会との共催で開始
2014年
1月 学校支援活動を再編、「教師相談」「研究者による支援」「教育ボランティア」を統合し「学校相談・教師相談」として開始
2月 定期総会にて「Ed.ベンチャー行動宣言」採択
教育講演会開催。テーマ:「『語るべき未来』を探る~原発事故が意味するものと『里』の思想」 講師:立教大学大学院教授 内山 節 先生
4月 『会報』に代わり広報紙『Ed.ベン便り』発行開始
12月 「生活相談」終了
2015年
2月 教育講演会開催。テーマ:「しんどい子を支えることはしんどい子のためだけじゃない」 講師:大阪大学大学院教授 志水宏吉先生
10月 合同理論学習会「第1回 学校教育につなげる労働をめぐるルール」開催。
11月 合同理論学習会「第2回 ブラック企業の実態と対処法」開催。
12月 授業研究会<小5・6教室>終了。
お父さんとお母さんのための日本語教室終了。「すたんどばいみー」の日本語事業に移管。
学校相談・教師相談終了。
2016年
1月 かながわボランタリー活動推進基金21ボランタリー活動奨励賞 受賞
2月 教育講演会開催。テーマ:「グローバリズムの果てを問う-新自由主義への決別と創造の意志-」 講師:文筆家・実業家 平川克美先生
3月 厚木在住の外国児童生徒を対象とした学習支援教室「Kokusai B.G」を終了。「エステレージャ・ハッピー教室」に統合。
合同理論学習会を「授業研究会(労働教育)」として継承。
第1回「外国人子ども支援ボランティア養成講座」開催。
4月 「産休・育休ママのための学習会」を開始
6月 神奈川県厚木保健福祉事務所委託事業として学習支援教室「Friends☆Star」開始
8月 第2回「外国人子ども支援ボランティア養成講座」開催。
11月 スタディーツアー実施。
2017年
2月 定期総会にて「新 行動宣言」採択
教育講演会開催。テーマ:「シフトダウンへの冒険 -「弱さ」の思想と生き方-」 講師:ナマケモノ教授・文化人類学者・環境活動家・明治学院大学 教授 辻 信一 先生
2018年
2月 教育講演会開催。テーマ「(この時代のわたしたちの)未来への責任-憲法論議の先に見えるもの-」講師:憲法学者・学習院大学法科大学院 教授 青井未帆 先生
2019年
2月 教育講演会開催。テーマ「原発労働と私たち・・・そして教育 知るべきこと伝えるべきこと」講師:ピアノ弾き語り音楽家・エッセイスト 寺尾紗穂 氏
2020年
2月 教育講演会開催。テーマ「ヤングケアラーを考える-子どもの視点から学校教育を問い直す-」講師:成蹊大学文学部 准教授 澁谷智子 先生
10月 教育講演会連続講座第1回(座談会)開催。テーマ「教育の不平等と学校の役割」話題提供:日本女子大学人間社会学部 教授 清水睦美 先生
11月 教育講演会連続講座第2回(講演会)開催。テーマ「教育においてICTを飼いならすために」講師:京都大学大学院教育学研究科 教授 石井英真 先生
12月 教育講演会連続講座第3回(講演会)開催。テーマ「なぜ、少人数教育が必要なのか」講師:東京大学大学院教育学研究科 教授 本田由紀 先生
2021年
1月 教育講演会連続講座第4回(座談会)開催。テーマ「偏見・差別・自粛警察を考える」話題提供:帝京大学文学部 准教授 山口 毅 先生
2月 教育講演会連続講座第5回(講演会)開催。テーマ「コロナ禍で考える未来の社会と教育」講師:同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科 教授 岡野八代 先生
2022年
2月 教育講演会開催。テーマ「児童虐待から家族・貧困・社会を考える-コロナ禍で置かれた女性の位置」講師:日本女子大学人間社会学部 教授 周燕飛 先生
2023年
2月 教育講演会開催 テーマ「逃れられない問題としての『女性の生きづらさ』」講師:東京大学大学院教育学研究科 教授 本田由紀 先生
2024年
2月 教育講演会開催 テーマ「未来への責任-平和教育を考える-」講師:東京女子大学 准教授 竹内久顕 先生
2025年
2月 教育講演会開催 テーマ「今の世界の現実を自分ごととして未来に向けて受け止める・・・核兵器をなくすために私たちにできること・・・」講師:カクワカ広島(核政策を知りたい広島若者有権者の会)共同代表 田中美穂氏
2026年
2月 教育講演会開催 テーマ「現在の学校教育のあり方を問う-わたしたちは「自発的隷従」から逃れられるのか」講師:関西学院大学 教授 桜井智恵子 先生