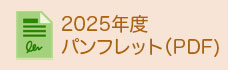理事推薦本
伊藤 剛 著、『なぜ戦争は伝わりやすく平和は伝わりにくいのか-ピースコミュニケーションという試み』(光文社新書 2015)
2月の教育講演会の講師、田中美穂氏(カクワカ広島共同代表)が講演の中で紹介されていた本です。著者は広告代理店勤務やフリーランスの雑誌編集者の経験を持ち、「ピースコミュニケーション」という新しい平和学のカリキュラムを作成して大学院で教えているという経歴を持っています。初版は終戦70年目に当たる2015年に発行されました。
序章は「コミュニケーションから考える戦争と平和」で、イメージや言葉などのアプローチから戦争と平和について次のように考察をしています。
戦争と平和は「対」として使われてはいるものの、戦争は「目に見え」、平和は「目に見えにくい」ことで「伝わりやすさ」において全く異なっている。「平和」を訴えようと思ったら、メッセージを投げかけられた人たちの頭に浮かぶイメージが異なるので、まずは各自の「平和のイメージを互いにすり合わせる作業」が必要になってくる。つまりコミュニケーションに「ひと手間かかる」ということだ。一方、戦争は「恐怖のイメージ」を一瞬にして多くの人々と共有できるので、コミュニケーションをしやすい。したがって戦争は伝わりやすく平和は伝わりにくいのである。
序章に続く第一部は「戦争のキモチを作るー三位一体モデル」で、権力者とメディアそして大衆の心理の三つの立場から、どのようにして「戦争のキモチ」が作られていくのかをひも解いています。「権力者の法則」では、権力者によって戦争シナリオがどのように作られていくのか、「メディアの構造」ではメディアがどのようにして偏向ニュースを作り出すようになっていくのか、そして「大衆の心理」では群衆の心理がどのようにして醸成されていくのかを説明しています。権力者とメディア、そして大衆が社会全体の空気(世論)を形成して「戦争のキモチ」を作っていく、三つの立場は互いに連動していて、「三位一体モデル」と呼べるような相互関係があるとしています。
第二部は「平和のココロをつくるー戦後71年目からの『問』」で、これからの平和教育を検討していきます。平和教育については、そもそも「平和を教育する」とはどういうことか?なぜ「戦争体験者」だけに話を聞いてきたのか?私たちの「戦争イメージ」は正しいのか?という三つの問いをもとに考えていきます。
最初の問いの中では、ドイツとフランスの間でお互いの高校の教室で「共通歴史教科書」が使われることになったことが紹介されていて、「フランス人のものの見方がわかるので、相手をより理解できるようになります。相手の考えを理解すれば、戦争はより起こりにくくなると思います。この教科書で学ぶことで二度と戦争が起こらないようになる、とまでは断言できませんが、相手への理解が深まるのは確かです。」という共通教科書を実際に使っているドイツ人生徒の言葉が印象に残ります。著者は、平和教育における国家の役割について「教育レベルで国民に何を学ばせるかを決めることではなく、他国との関係を構築する外交レベルの方がより重要な意味を持っているのではないだろうか。」とまとめています。
二つ目の問いでは、戦争体験者ではないエジュケーターという役割を紹介し、アウシュビッツ・ミュージアムが紹介されています。その中で、収容体験者の一人で、かつてのミュージアムの館長がミュージアムを訪れたドイツの若者に対して投げかけた「君たちに戦争責任はない。それでもそれを繰り返さない責任はある。」という言葉が印象に残ります。著者は「この言葉には、戦争の歴史を学ぶ本来の目的が示されている。戦後70年間、私たち日本人は体験談にこだわり続けて戦争を学んできたが、一方で「くりかえさない責任」のために知ることを学んできただろうか。」と投げかけています。そして、「これからは聞き続けてきた体験談を土台にして、私たちの『当事者性』を取り戻さなくてはならない。戦争体験者だけが『当事者』ではないのである。」とまとめていて、今後の考えるべき方向性を検討しています。
そして最後に、さらにもっと大きな視点で戦争と平和について考えるための「本質的な問い」を紹介しています。これらの問いは正解のない、「ジレンマ」をキーワードにしたもので、著者は「戦後71年目からの宿題」のようなものであるとして、三つの問いを投げかけ、読者が新しい問いを見つけて考えることが戦後71年目からを生き続けていく私たちの宿題だとしています。
今年は戦後80年となる年で、この本が発行されてから10年が経ちます。今、戦争体験者が約一割と少なくなり、次世代に戦争の記憶や記録をどう伝えるのかが課題だと言われています。この本は平和教育の目的を再確認して、これからの平和教育について考える参考になります。(SH)