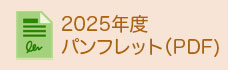事例研究会は、外国にルーツを持つ子どもたちの具体的な事例を通して、かれらの背景にある事情や問題を読み解く力をつけていくというねらいで開催しています。9月・10月は連続した内容での研究会となりましたので、あわせて報告します。
【事例研究会9月10月報告】
日時:2025年9月17日(水)、10月16日(木)いずれも19:00~21:00 オンライン(Zoom)
事例:「いろいろな課題を抱える子どもの事例」
事例提供:大和市内中学校教諭
参加者:9月17日:6名、10月16日:5名
9月10月は、連続した内容での研究会となりました。
9月は、中学校の先生から中国ルーツの子どもの事例を提供していただきました。小学校では持ち物や提出物が揃わなかったり、宿題をやってこなかったりといったことがあり、中学生になってからはクラスのみんなから嫌なことを言われると担任に相談を持ちかけ、体調不良を理由に保健室に毎日通っている子どもの様子が報告されました。報告を受けての協議では、学校は子どもを育てる場で、子どもの意思表明を保障していくことが重要であることを確認しました。アドバイザーの先生からは、子どもとの会話を通して、子どもが選択して納得する場面をどう作っていくかが重要であること、子どもとの会話から格差を確認してその格差を埋めるために何をするのかを探し、子どもの資源を増やしていくことが重要であることというアドバイスがありました。そして、事例で紹介された生徒との会話を深めて子どもの背景や置かれている状況、子どもの思いなどをより詳しく把握する必要があることが確認されました。
10月は、9月の協議を受けて当該生徒の話を聞き取った結果を報告していただきました。子どもと会話を重ねる中で、9月の報告では分からなかった子どもの背景がより明らかになったという報告とともに、話を聞いたことで子どもとの関係がより深まっていったこと、そして子ども自身の学校生活が上向きになっていることなどが報告されました。今回は子どもとの対話についての協議が中心となりました。協議では、対話することの意義は何なのか、話を聞くポイントはどんなことかといったことが話題となりました。アドバイザーの先生からは、対話の意義には、話すことを通して自分を客観視することにつながること、問われることで言葉を獲得し認識が豊かになっていくことというお話がありました。また、対話をしていて子どもが「分からない」という状況が出てきた時には、言葉がないから分からないのであるから聞き手が言葉を置いていくことで言葉の獲得につながっていくとのアドバイスもありました。
外国人の子ども理解のための学習会では、昨年度「対話」をテーマにした学習をしました。9月と10月の事例研究会は昨年度のテーマにつながる内容となりました。聞き手が対話の持つ意義を理解したうえで子どもとの対話の時間を作り出すことが必要だと感じます。今、学校は先生も子どももとても忙しい場所になっていて、対話する時間が取りづらいという面があるかと思います。外国ルーツの子どもにとっては、対話をすることは自分が受け入れられている、認められているという安心感を持てることに繋がり、言葉を獲得したり知識を増やしたり、資源を増やしたりする機会でもあることを今回の研究会を通して再確認しました。昨年度のテーマが再び取り上げられたということから、外国ルーツの子どもにとって、対話をするということが重要な支援の形だということだからです。国語や社会科といった教科学習の知識をつけることだけに支援が向くのではなく、子どもの資源を増やしていくための支援を意識して子どもと向き合うことが必要だと感じます。