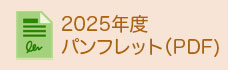学習会報告
日時:2025年3月29日(土) 10:30~12:00
参加者:11名
内容:「参加者それぞれの現場から排除の実態を報告し合い、現状を認識する」
今回の学習会では、小学校、中学校で見られる”インクルーシブでない状態”について語り合いました。
国際級在籍の生徒に対して試験問題にルビを振らない教員がいる。以前ほど教員が家庭訪問を積極的に行わなくなった。我が子の人間関係に過敏な保護者に対して毅然とした態度を示せないなど、様々な苦しさを抱える子どもに対して、出来ないことを学校・教員の責任を子どもに押し付けてしまっている現状。また、教室で子ども同士が多様性を認知し、受け入れるまでにかかる時間を学校が確保しづらくなっている現状が指摘されました。学校に通う子ども以上に、教職員集団や保護者の意識についても話題が及ぶ有意義な時間となりました。
今回確認された現状を踏まえ、参加者各々がどのように子ども、そして職員集団・学校現場の抱える課題と向き合っていくのか。8月の学習会に向けて考えていきたいと思います。
【参加者の感想より】
・保護者としてと特別支援の方が手厚いからという感覚、すごく分かります。「インクルーシブにするよ」「学級を20人にするよ」が実現したらいいな..と思います。インクルーシブの理念と政策のズレが矛盾がすごく感じられて、意味のないことをどんどん進めているんだなと思いました…。クラス替えが1年ごとなのはリスク回避になるということをはじめて知り、年度替わりに毎年不安定になる子どもたちを考えると、本当に大人のためのクラス替えなんだなと思いました。
・最近、教育と労働の関りに関する議論をした。剰余価値を増やすためには、2つのパターンがあるという。1つは単純に労働時間を増やすということ、もう1つは短時間でより多くの価値を創出可能な労働者を使役すること。教育は後者に関わっているという。今日の議論をきいていると、現状の教育は効率的な生産者を産み出すことに焦点化した教育の形に近づいているように感じる。その一方で、必ずしも教育現場で行われていることが効率的な生産者の生産に寄与するわけではないだろう。インクルーシブ教育もその一つである。インクルーシブ教育は基本的に生産性を高めることに直結するわけではない。生産性と関連の低い教育活動の価値を再確認するべきだと考える。
・学校がインクルーシブになることには、教師意識だけでなはなく保護者の意識や制度的なものなど、様々なハードルがあることを理解しました。インクルーシブをすすめることは、とても難しく思うようにいかないのだろうと思います。「(多様性の認知・受容に基づくインクルーシブの実現には)時間とお金がかかる」という言葉が印象的でした。効率を重視する学校の中で、子どもたちがますます生きづらくなっていくのが予想されるだろうなと思うとやりきれないです。
・東京、日本だとその子に合わせた分離することをインクルーシブと言っている現状がある中で、「インクルーシブ」というものを話すことがまず大事なのだなと思った。
・自分の学校でいかにインクルーシブの考えが実践されていないかを痛感しました。また、この1年で自分が日本の学校教育の悪いところにとりこまれて、大切な考えが失われていたことにも気付きました。
・学校現場での「インクルーシブではない実態」が報告され、とても参考になった。学校の教室そのものが持つ理念が、インクルーシブから離れてしまっていることがよくわかった。
・インクルーシブな社会を目指すには、自分も学校の中で考えを戦わせたり、もっと理解を深める取り組みが必要で、まだまだフォローしきれていない子どもがたくさんいると感じた。
・何のために学校があるのか、教室をどんな場所として位置づけるのか、改めて、突き詰めて考えていかなければと思いました。担任をしていた頃、学級目標を温かいクラスとして、運動会や合唱コンでは、力を入れずにのんびりと学級経営をしていましたが、今は難しいのですかね。
・子どもと生活していく中で、自分のした行動、言葉掛けで子ども同士の関係性が分断されたと感じる場面があり、あのときの反省を振り返ることができました。「子ども主体に」と言われ続ける教育現場で、子どもを誘導する教師の責任は問われず、何かあったら子どもの責任、問題を子どもに求めている実態があることを認識して、違和を行動や言語化して伝えていくことを目標に教育に向き合っていきます。
・子ども、教室のインクルーシブの前に職員間のインクルーシブを実現する必要性を感じる。意見を交換するための時間、また教育観・価値観をすり合わせることにもっと時間をかけたい。特に、若手とベテラン、20代と50・60代の教職員の乖離をつなぎ留めたいと思っています。