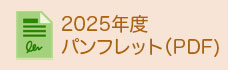2017
-
内 容 「文献講読 加藤彰彦著『貧困児童~子どもの貧困からの脱出』(創英社/三省堂書店) 日 時 2017年11月6日(月)19:00~21:00 場 所 大和市文化創造拠点シリウス603号室 参加者11名 11月の理論学習会では、「貧困児童」という本で文献講読会をおこないました。6章で別れている本の要約を各章一人ずつおこない発表しました。その後は参加者で本を読んだ感想や「子どもの貧困」の現状について話をしました。 「貧困」は絶対的貧困と相対的貧困に分けられます。日本で貧困問題を考えるとき、この相対的貧困について考えます。(相対的貧困とは、「現在暮らしている社会のほとんどの人が享受している『普通の生活』をおくることができない状態」をいう。:文献より抜粋)衣・食・住ができないことを「貧困」とイメージしていると、現代の日本における「子どもの貧困」という言葉は理解しづらいのではないかと思います。今回、文献講読をおこない、日本における相対的貧困である「子どもの貧困」の状況を理解するとともに、背景としてお母さんやお父さんの置かれている厳しい現状もあるということを知りました。 後半の話し合いの場では、自分の周りにいる子どもたちがどのような状況に置かれているのか、また、今日の社会の中では、これまで「親として当たり前」と思われていること、「親として当然」ということが非常に難しい現実があるということがわかり、そのことが子どもたちの貧困へと連鎖を生んでいることも知りました。多くの貧困家庭を支援する(サポートする)制度があっても申請主義をとる日本の中では、手続きをすることが大きな壁となっている現状もわかりました。 学校は、教師は、子どもたちとどう関わっていくのか、どのように家庭に入っていくのか、学校ができることは何か、ということについても話がされました。「子どもの貧困」の現状を話をする中で、学校が持つ可能性の実践として「学校が制度を家庭に伝えることで、手続きをすることができた」という話もされました。 学校が、教師ができること、そして、子どもたちにどんな力をつけさせるか、何ができるのか、「子どもの貧困」という問題にどう立ち向かっていくのかを改めて考えさせられました。 できることは多くあるのかもしれません。でもまずは「自分のまわりにいる貧困児童に気づくこと」。この第一歩をしっかりと出せるようにしたいと思います。 <参加者の感想:一部抜粋> 貧困ということについて初めて真剣に考えました。全てのことについて当たり前だと思わないこと、教員としてどこまで家庭と関わっていくか、とても勉強になりました。これからは今自分ができることはやっていきたいと思ったと同時に、生徒との関わりを今以上に大切にしていきたいと思いました。中学校教師 みなさんから色々な具体的なお話を聞くことができてとても勉強になりました。少し考えてみると身近に“相対的貧困”に当てはまるであろう生徒が何人も思い浮かび、はっとしました。明日から少しでも私にできることをやっていかなければと思いました。中学校教師 学校ができること、教員ができること!といってもますます厳しいな、と思ってしまいます。学校が家庭を支援する視点はだいぶ現場にもあると思いますが、やはり、子どもたちがこれから生きていく上で、公的サービス、支援について知ること、考えること、行動できること、人とつながること、そんな力をつけていけるようにしたいです。小学校教師
2017年11月28日 理論学習会 11月 再考:子どもの貧困
-
内容 『子どもの貧困~からだ・こころ・性~ 』 講師 金子由美子先生 さいたま市生活困窮者学習支援事業代表 日時 2017年 10月2日(月)19:00~21:00 場所 大和文化創造拠点シリウス603号室 参加者 12名 保健室という現場で、性教育や思春期の子ども達への取り組みを実践されてきた金子先生。現在は、さいたま市で生活保護または児童扶養手当を受けている子ども達に無料で学習支援を行う事業の中心で活動され、若者たちの居場所づくりに奔走されている。常に、実践の中にいる先生のお話は、若者たちの生きづらさを語るものだった。 貧困やそれに関わる複合的な困難による子ども・保護者の感情や行動に目を向け、子どもをみる時のまなざし(不登校、基礎学力、体力、塾、友達、学校行事、部活、給食、など)、家庭の問題(身支度、食事、リーガルリテラシー、識字能力、疾病、外国籍、親せき、ネグレクトなど)を、貧困状況にある子ども達への視点のポイントを具体的に挙げてくださった。学校現場で、私たち教師が子どもに出会うときは、何か問題が起こったり、学校から離脱したりと具体的な出来事から、その背景を知ることになる。その時に、複合的な視点から、分析することが具体的な手立てへの一歩になると感じた。 「人生は長い、長いステージ」という金子先生。親の離婚や再婚、シングルマザーの厳しい現実、大変な生活の中に身を置き、自分を表現できず苦しむ子ども達、子ども達との出会いと関わりを具体的な事例から語る中に、おとなになることが困難な子ども達の姿が想像された。「思春期はさなぎ」と言い、「思春期の育ちなおし」ができる社会、大人のサポートが大切だとおっしゃった。自分の力で自分をつくりだすこと、 そのために大人が見守っていくことが大事だというお話が印象的だった。 今回の学習会には、高校生や養護教諭、様々な年齢層と立場の参加があり、それぞれの立場から、どう子どもに寄り添うか、という話も出た。様々な困難を抱える子どもたちを前にしたとき、 自分に何ができるのかと考えてしまうこともあるが、見守れる・寄り添えるだけの知識と言葉を身につけ子どもたちが生きる今に寄り添える教員になりたいと改めて感じた学習会となった。 多くの事例から、子どもたちのおかれている現状の大変さを認識しました。私も一養護教諭として苦しんでいる子を見逃していないか、日々振り返りながら職務にあたっていきたいと思っています。こうして、定期的に学習会を開催している皆様に敬意を表したいです。また、参加させてください。(養護教師) 多くの経験談を聞かせていただきありがとうございました。家庭内のトラブルによって大人への不信、学校不信、人間不信にもつながるのではないかと、先生の話を聞いて思いました。家庭内に「なにか」ある子に気づき、相談できる環境をこれからも整えていきたいです。(小学校教師) 家庭が安心できる場ではない子たちのSOSを周りの大人がキャッチして救ってあげられるようにしなければと思いました。そのために、子どもたちの置かれている状況を知ること、アンテナをはって子どもと関わっていくことが大切だと感じました。貴重なお話をありがとうございました。(小学校教師) 今日はありがとうございました。大人との関係性の再構築という言葉が印象に残りました。家庭や教員と問題が発生し、子どもたちから話を聞く機会があるのですが、子どもたちがどんな風に大人を見ているのか、あまり考えずに来ていたなと思います。明日からこの視点を持って接していきたいと思います。(中学校教師) 大和市内でも性教育についてはずーっと続いていたのに、多忙化や学習内容が増えたことでなおざりにされてきていることにこれではよくないと危機感を持っています。これからの教員一人が命と性に対しての学習を深め子どもたちに生きることの素晴らしさを教えていってほしいと思います。(小学校教師) 日々向かい合っている生徒たち一人1人にできることって何だろうと考えています。『思春期はさなぎ』と伺い、「たしかに自分もそうだったな」と当時を思い出しました。私自身女子校で12年間を過ごし、今思えば、かなり偏った教育を受けてきたかもしれません。でも色々な価値観があることを知り、色々な環境で育った子どもたちがいることを知って、子どもたちと一緒にこれからも学び、成長していきたいと思っています。(中学校教師) 色々な環境で生活をしている子がたくさんいるということ、つらい状況におかれている子の現状を知ることができました。そのような環境におかれている子がどんな場所でもいい、どんな人でもいいので、「話ができる」ということがとても大切だと思いました。話をすることもとても勇気がいることだと思います。少しでもその勇気を出せる、出してもいいかなと思ってもらえる存在になりたいと思いました。ありがとうございました。(中学校教師) 子どもたちを取りまく家庭、学校の様々な問題とそれに関わる先生の実体験などもお話しいただき、とても勉強になりました。最後にお話しいただいた『さなぎ』のお話がとても印象に残りました。思春期のさなぎの子どもたちが自分で自分を見つけ飛び立っていく支えになれる存在でありたいと思いました。本日はありがとうございました。(中学校教師) 今まで自分は不幸な家庭だと思っていました。ですが、今日の金子先生のお話を聞き、自分の家庭は普通幸せなんだと気付くことができました。ボランティアをしていく中で、今日お話ででた子どもと会うかもしれません。どう接したらよいのか分からなかったら、金子先生に相談したいと思いますので、その時はどうかよろしくお願いします。(高校生) 心と体の健康に加えて、セクシャルエルスという側面からのサポートが必要というお話があり、納得しました。性化行動も初めて聞くお話で、分かって生きていることも増えてきていると理解しました。この分野をもう少し追いかけてみたいと思いました。(大学教師) どの地域でも大なり小なりの子どもの抱えている問題があるのを再確認した次第です。先生がこの世界に踏み込みたいと思うほど、子どもたちが窮地におちいっているのをもっと切実に感じなければと思いました。本日は参加させていただきありがとうございました。(養護教師)
2017年11月27日 理論学習会 10月 思春期のさなぎたち
-
内 容 「母親を励ますことで、子どもを育てる ~生活綴方の実践を通して~ 」 (講師 伊藤久美子先生 埼玉県所沢市立宮前小学校 ) 日 時 2017年9月2日(土)14:00~16:00 場 所 大和市文化創造拠点シリウス603号室 参加者9名 9月の理論学習会では、伊藤久美子先生を講師としてお招きし、先生が小学生の男の子を担任した時の『記録』をもとに、生活綴方の実践をお話していただいた。周辺の子とは違った行動をする男の子の子育てに悩むお母さんと綴った5冊にもわたる連絡帳がその『記録』である。 伊藤先生の生活綴方の実践からは2つの変化を見ることができた。1つは教師が寄り添い、励まし続けることにより前向きになっていったお母さんの姿。そしてもう一つは、男の子が自分の言葉で表現することができるようになっていった姿である。 その背景には、先生がお母さんを毎日のように励まし続ける言葉、子どもを見守る温かい言葉であふれていた。教室の中で乱暴な行動に出たり、自分の髪の毛を切ってしまったり、いろいろな行動をしていた児童が『言葉』を獲得することで、自分の気持ちを表現できるようになり、お母さんを悩ませていた行動も少なくなっていった。 『言葉』の獲得には伊藤先生の丁寧な取り組みがあり、「書いてあげるから言ってごらん」と、その児童の気持ちの表現を出すということから少しずつ自分の言葉として書くことを覚えていった。彼は「それまでつらいこと、悲しいこと、くやしいことは、きっと、心の奥にしまって出さなかったのだろう」、「出せなかったから勝手な行動に表れた」と先生は語った。実際に、自分の思いを出すことができるようになってからは、彼の行動は落ち着いていった。 先生は、困っているお母さんに対して「(先生が)困ったことは書かなかった」と言う。そのお母さんがどれだけ大変な状況の中で子育てをしてきたか、そして、どれだけつらい思いをしてきたか、それを先生は知っていたし、これ以上お母さんを責めることをしなかったのだと思う。それよりも先生が選択したのは、一文字一文字、言葉でお母さんに寄り添い続けることだった。 「母親を応援することがその子を育てることに繋がった一年だった」と先生は語っている。この『記録』の中でお母さんの「今は子育てを楽しめるようになった」という言葉が印象に残った。伊藤先生の実践はとても心温まるものであり、教師ができることの可能性を教えていただいた学習会だった。 参加者の感想(一部) 学習会に参加できて、本当に良かったです。自分なりには子どもたちや親の気持ちに寄り添って、実践してきたつもりですが、今日の伊藤先生や佐藤先生のお話でまだまだだと実感しました。信頼関係を築くことが、自分のことを語り始めることにつながるのだと痛感しました。寺子屋に集う子どもたちとも、こういうつながりを大事にしたいと思いました。(元小学校教師) 伊藤先生とT君のお母さんとのやり取り、またお母さん、Tくん2人の成長のお話、とても感動しました。また、伊藤先生の保護者、子どもとの向き合い方、とても勉強になりました。私も少しでも子ども、そして保護者に寄り添える教員を目指して子ども・保護者と向き合って行きたいと思いました。(中学校教師) 本当に感動しました。お母さんにとって本当につらい時期に伊藤先生のひと言ひと言でたくさんたくさん救われたんだろうな、と実践を聞いて思いました。(経済的・社会的)貧困からくるお母さんのつらさと先生の言葉から伝わるあたたかさを想像し、何度も胸が熱くなりました。自分を語ること、綴ること、記録すること、その大きな意味をとても感じました。ありがとうございました。(中学校教師)
2017年09月24日 理論学習会 9月「言葉」を獲得すること
-
内容 『女性の貧困から見えること』 講師 首都大学東京 杉田真衣先生日時 2017年 7月3日(月)19:00~21:00場所 大和文化創造拠点シリウス603号室参加者 10名 多くの教師は、困っている状況にある子どもを「何とかしたい」と働きかけようとする。その時、お母さんたちの問題にかなり多くの教師が直面することだろう。貧困という言葉の下にある現実は、労働、孤立、暴力…様々な問題を抱えている。子どもの貧困を考える上で、女性の貧困の状況を知る必要があるのではないかと考え、今回は長く女性と労働に焦点をあて研究されている杉田先生をお呼びして話をしていただいた。女性の貧困がなかなか語られない背景に、女性は夫に養ってもらえばよい、それゆえに女性の労働は、非正規、低賃金でもよいとされてきた経緯がある。男性すら非正規労働の中にあり、養ってもらえない女性たちが、労働の問題に直面し、その問題が明らかになってきたのである。 杉田先生の高卒女性たちが30歳になるまで追い続けたインタビュー調査からは、女性たちの現実が浮かび上がってくる。 貧困状態に陥る女性たちの多くは、学生時代から家庭の状況が落ち着かず、生活のためにバイトをしていたり、落ち着いて学習できる環境になかったりしる。彼女たちが、正規の仕事に就くこと、奨学金を申込み進学できること、はとても高い壁がある。非正規で安定した収入を得られない中で、正規なみに働かされる。仕事を通じて、アイデンティティを形成することが難しく、将来展望も描けない。経済的自立の困難は、明白であった。今ここにいるという感触を得られる関係や場が、女性たちのこれからにとって重要な意味をもつ。どこにもアクセスできないお母さんたちが、子どもを通じてかろうじて学校にそれを求めることは、自然な流れなのかもしれない。ただ、学校はその道の専門機関ではない。親の状況を個人の問題と片づけることなく、やはり専門機関と手を携えて親を支えていくことが必要だ。学校が、お母さんの困り感を受け止め具体的な方策として行政につなぐ、ということも実際にあることのようだ。地域の中に、居場所のような場があることが、今後は必要であるのかもしれない、と先生はおっしゃった。 学校以外にも、生活していくために必要な情報が得られ、場合によっては専門機関につながれる場であると同時に安心していられる居場所をあちらこちらにつくること。そして、女性たちが生きていく上で必要な知識や技術を伝える事。妊娠や性感染症、暴力、依存症を含む病気、労働のルール、生活保護や育児支援、先生が挙げた具体例は、生きる上で知るべきことでありながら、タブー視され学校現場で正面から扱われることは少ない。この点についても、教員の立場からアプローチできることがあるのではないかと、今後の課題をいただいたように思う。10月の学習会では、元養護教諭の金子先生をお招きし、性と女性の問題をお話ししていただく予定なので、そこでさらに勉強していきたい。 ◎以下、参加者の感想一部抜粋 女性の貧困の現実を感じました。特に仕事に対する自己満足感のなさ、金銭的な貧困とこれは深い結びつきがあると思います。仕事をしていく上でのやりがいやアイデンティティの形成こそ、私たちが仕事をする大きな意味なはずなのに・・。目の前の子どもたちに何ができるか、もっと具体的に、もっと実践的に考えていかなければいけないと実感しました。いつも貴重な学びの機会をありがとうございます。(中学校教諭)自分の想像を超える女性の貧困の実態をお聞きして生きていくことの困難さを感じました。子供を抱え、一人親の母親など、目の前の生活にいっぱいいっぱいで、余裕がない中暮らしていることを思うと学校としてできることはしていきたいと思いますが、社会としてそのような女性を救う場所、制度、支援をもっと整えていって欲しいと思いました。(小学校教諭)4人の方のお話を聞くと、人への依存が高く強く、そこから大変さにつながっている場面もあるのかなと思いました。一方で友人との関係性の中で保たれている部分もあり、依存の善し悪しがあるのかなと思いました。学校の中で知識として伝えるときに、どこまで自分の将来に繋がっていることとして教えられるのか、また生徒の親が生活保護や非正規労働、様々な病気等、「今その状態」の中でどこまで教えていいのか、教えることができるのか、難しいなと思いました。(中学校教諭)今日はありがとうございました。「女性の貧困」について知っていると思っていただけで、実はその人たちがどんなふうに生きているのかは、よくわかっていなかったんだなと言うことが、今日のお話を聞いて分かりました。社会は貧困を「その人のせい」としてしまいがちだと思うのですが、決してその人たちが怠けたり楽をしたりしているわけではない。どうしようもできなくて「貧困」という状況におちいっているだけだということをもっと多くの人が知らなければ、日本という社会は良くならないなと思います。考える、とても良い機会をあたえていただきました。ありがとうございました。(小学校教諭)今日はありがとうございました。「男性」と「女性」の違いがとてもよくわかりました。やはり女性は苦しい立場に置かれることが多いと思います。それは日本の歴史の流れもあるとは思いますが、これから貧困を抱える女性を、どのようにサポートしていくか。地域や社会とのつながりの必要性をとても感じました。また、その貧困が連鎖をしていくということも気になるところです。その連鎖を断ち切るためにも、やはり地域とのつながり、そして、子どもたちをその連鎖から抜け出すために、学校として何ができるのか、これからも考えていきたいと思いました。ありがとうございました。(中学校教諭)
2017年07月21日 理論学習会 7月理論学習会報告
-
内容 『子どもが考える授業づくり』 (講師 小田原市立白山中学校 柏木 修先生) 日時 2017年 6月5日(月)19:00~21:00 場所 大和文化創造拠点シリウス603号室 参加者 5名 「野宿者問題」を授業で取り上げる柏木先生から、貧困問題を取り上げる際の視点、授業展開の視点を学ぶ学習会となりました。 先生は、語教育(国語教育)の目的は主権者を育てたい、自分の意見(思想)を持った人を育てたい、幼児化している生徒を知的にしたいことなんだと明確な姿勢をもち、「野宿者問題」の他に、「ゲイや性同一性障害の人たちと出会う」「死刑制度」など、様々な問題を授業で取り上げています。それらは、社会が 痛みとして抱えるべき問題でありながら、見て見ぬふりであったり、排除であったりという形で正当に取り上げられることが少ないことばかりです。いじめを考える、少数側を考える学年づくりを考えて、このような授業をされているというお話から、学年規模での想定に驚きました。 柏木先生の授業は、テーマに関連する本を読んだり、憲法の精神を学んだり、当事者と生徒が実際に出会う中で、生徒が考えを深めていきます。自分自身と対話し、また他の生徒と紙上討論を経て対話することで、考えを深めていくのです。 野宿者問題を考える授業では、「『ホームレス』に出会う子どもたち」(一般社団法人ホームレス問題の授業づくりネット)DVDの視聴、「どんとこい、貧困」(著 湯浅誠 イースト・プレス)講読、権利の視点からの憲法学習などを通して、生徒たちが自分自身の考えを何度も見つめなおすことになります。自己責任論を乗り越え、人として自分は何を大切に生きていくべきか、社会の在り方をどう考えていくべきか、とことん真剣に考えます。それは、主権者である自分として生徒たちが知的に変容していく姿でもあります。最終意見は、定期テストの「書く」テストで表明します。 「政治が変われば、世の中も変わる。学んでいかないと、もっていかれるんだ。」という先生の言葉に、授業の可能性、集団としてともに学ぶ可能性を強く感じました。貧困問題は、誰にでも起こりうることです。自分の持つことが、自分を守ることにつながるのだと思いました。「自分も生徒との対話を通して乗り越えていく、変わっていける。」とおっしゃった言葉が心に残りました。 運営面としては参加者が非常に少なく、大変残念でした。エドベンチャースタッフや周囲への声掛けが課題です。 ◎参加者の感想(一部) とても勉強になりました。本当におもしろいお話ばかりで、先生の実践や子どもたちの意見を聞いていたら、何だかワクワクしてしまいました。「自分を見つめ直す」という言葉から。私自身も『考える』ことをもっとしたいと思いました。『考える』ことの楽しさをもっと子どもたちに体験・経験してほしいと思うと同時に、そういう授業の展開を目指していきたいとおもいました。ありがとうございました。(中学校教師) 型にはまった授業からは学べないことを学べるなと思いました。「自己責任論を『のりこえる』」ということは私にも必要だと実感しました。また、国語の授業の工夫も大変勉強になりました。今日伺ったこと、ぜひ私も授業に取り入れてみたいです。本当にありがとうございました。(中学校教師) 大変、おもしろい報告で、勉強になりました。自分自身の考えを整理するために、子どもと対話し、自分をのりこえていくというお話がためになりました。(大学教師)
2017年06月19日 理論学習会 6月 理論学習会 報告
-
内容 『子どもの主体的な学びと生活綴方―「学力」支配から自由になる―』 講師 和光大学 奥平 康照先生 日時 2017年 5月8日(月)19:00~21:00 場所 大和文化創造拠点シリウス603号室 参加者 11名 1951年3月に無着成恭が発行した『山びこ学校』(青銅社 現在:岩波文庫)から、生活綴方の実践をみた。この山形県山元村という貧しい村にある学校での実践は、『子どもたちの生活記録』で、それを学級文集にしたものだった。ある生徒は『雪』を、ある生徒は『母の死とその後』をタイトルに、自分自身の感情を記録している。その『記録』は正直な子どもたちの生活が記されていて、「どうやったら貧乏から抜け出せるか」、真正面から考えようとしているものだった。1人の子が抱える困難を学級の生徒が支える。子どもたちが自分の貧困を見ようとする、子どものつらさを教師が知る、そして寄り添い、支える。そんな実践をみることができた。 生活綴方は子どもたちの共通の課題に取り組むときにとても有効であるが、1960年代から生活綴方が消えていった。共通の課題であった『貧困』は、国が豊かになり、特別な課題となってしまった。 今、生活綴方を実践しようと思ったとき、子どもたちは自分の生活記録を真正面から記せるのだろうか。周りの生徒との生活環境の違い、経済の背景、様々な自分自身の課題を見つめた生活綴方ができるのだろうか。「貧困」を隠さず記し、自分の課題として学級文集にできるのだろうか。また教師は、その子どもたちの本当の課題を真正面から受け止めることができるのだろうか。子どもたちの抱える生活にまで入り込んで一緒にその子のつらさに寄り添い、一緒に解決へ向かっていく覚悟を持てるのだろうか。そんなことを考えさせられた。 また、生活綴方は、「子どもたちが本当に学びたいことは何か、見つけなければならない」ということの問いにもぶつかる。学校で学ぶことと本当に子どもたちが学びたいこと。 これからの社会をつくり生きていく子どもたちが、自分たちの課題を見つめ、解決する力をつけるために教師は何ができるかを考えるきっかけとなる学習会であった。 ◎以下、参加者の感想一部抜粋 「生活の課題を見つめ取り組むこと」 今を生きる子どもたちにとても必要で大切なことだと思いました。学力向上が注視される中で一人一人が抱える課題をキャッチしていかに寄り添えるか、教師としての技量を高めなくては、と思いました。 実感を持った日々を切り取らせること、自分の感情をそのまま表現させること、現代の子どもたちにとっては、難しい部分もあると思います。でも、この仕事に就き、日々子どもたちと過ごしている今だからこそ、できることがあるとも感じました。子どもと“ともに”辛いことも嬉しいことも分かち合える教員でありたいです。 子どもたちが自分の生活をありのままに書く、書けるようになるには教師と子どもたちの距離がとても大切だと思いました。子どもたちの現状を、苦しいことも悲しいこともその実態を教師がしっかりと見つめ、寄り添うことができなければ、成り立たないと思いました。ただ、その苦しさ、悲しさをその子の周辺にいる子どもたちが共有するということは、様々な家庭環境がある現代では難しさを感じました。ですが、子どもたちにできるだけ寄り添い、今できることをしたいと思います。 「子どもたちが学びたいことを子どもたちと一緒に探す。ただし、子ども自身も何が学びたいかわかっているわけではない。」 というお話が生活綴方を端的に表しているようで、久しぶりに色々と思い出しました。現代版の生活綴方を先生方と一緒に考えていきたいと思います。
2017年05月21日 理論学習会 5月理論学習会の報告
-
内容 『学級づくりの基本―子どもたちをどう捉えるか―』 講師(日本女子大学 清水睦美先生) 日時 2017年 4月10日(月)19:00~21:00 場所 大和文化創造拠点シリウス603号室 参加者 23名 新学期をむかえ、子どもたちとの新たな一年を構想する教師たちにとって、学級をどうつくっていくのか、子どもたちをどうとらえていけばいいのかという視点は欠かせない。 集団作りの技術として、教室を「集団」」として見た時の子どもたちの位置取りを中心、周辺、様子をみてリスク回避する子に分類し、集団を捉える視点や、いじめの構造を加害者、被害者、観衆、傍観者に分類し、いじめのタイプを捉える視点を示していただいた。トラブルの当事者だけでなく、それを取り巻く周りの子たちの位置取りや関わり方こそが重要な糸口であり、正しく捉えることが大切だということが明らかになった。 学校がまとまるとき、排他的な雰囲気が生まれ、みんながまとまる行事ほど、雰囲気が一元化し、いじめが起こりやすいという話に、若手教員たちは、「今までまとまることがいいことだと思っていた。」「団結しよう、と子どもに言っていた。」と自身の教育活動が意味することを振り返り、これからの学級集団において何を目指すべきかという問いにぶつかった。 そこで、清水先生からは、教室を多様な価値を学ぶ場と位置付ける事、教師は個人としての価値観を磨くこと、が必要だというお話があった。教室の中で、誰がどんな思いをしているのかという関係性へのアンテナを高くもつことで、子どもたちは、関係を編み直し、多様な価値観を学んでいくはずである。雰囲気の一元化を助長するのも教師、壊すのも教師。教師のもつ権力がいかに学級集団に影響を与えるのかを考え、これからの一年を過ごす子どもたちに、集団としての力をつけることができるのだろうか、ということを参加者自身が考えるきっかけとなった学習会となった。 ◎以下、参加者の感想一部抜粋 周辺として中心をつくる経験を学ぶということころが、難しいけれど大切だと感じました。 小学校の活動には効果的なものが多くあると思います。授業だけでなく係活動や行事など一つひとつを学級集団をどう形成していくかと照らし合わせることが重要だと思いました。:小学校教員 学級の雰囲気から・・・(ヴァルネラヴィリティ)は中学校の世界ではわりと多く習慣・文化として残っているものだと感じます。世代が違うと価値観も当時、通用していたことも通用しなくなるのは当たり前のことですが、日々の忙しさと経験の少なさからそのような習慣に楽だからすがるような場面(先生)を多々見てきたので、まずはそのような考えや習慣を断つとことから自分は始めようと思います。:中学校教員 集団の位置取り・関係づくりの難しさを感じました。教室が、ただ子どもたちが群れる場ではなく、多様な価値を学ぶ場となるよう、自分自身が価値観を磨き、柔軟な部分と一貫した部分をはっきりとしっかりともてるようにしていきたいと思います。これから学級経営をしていく中で、今日の学びを自分の中に落とし込んで行きたいです。 現場では、「対集団」ではなく、「対個人」への対応が求められています。いろいろな生徒がいる教室の中で、その「個」をどう集団の中に位置づけ、子どもたちどうしの関係をつくっていくにはどうしたらいいのか、最近考えています。また、「リーダー」を固定化させている現状にも反省です。もう一度、自分の学級経営を考え直そうと思いました。「個々人が大切にされる」そんな学級集団をつくりたいです。
2017年04月20日 理論学習会 4月理論学習会の報告