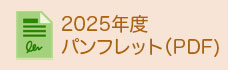2020
-
6/6理論学習会報告 テーマ:支援が必要な子、弱い立場の子を周りの子との関わりの中で育む 報告: 岡部千春 教諭(大和市立上和田小学校) 日時: 2020年6月6日(土)13:00~15:00 Zoomによるオンライン開催(参加人数16名) 今回もzoomを使ってオンラインで学習会を行った。 最初の約40分間は、岡部教諭からこれまでの実践を報告していただいた。 岡本教諭は「誰にでも支援は必要!」という話から始められ、「担任として大切にしていること」をベースに、子どもたちとの関わり方を事例とともに報告された。 そして「誰も完璧じゃない!安心していられるクラスに」すること、子どもたちを「困らせない・イライラさせない工夫をする」こと、「ドアも心もオープンに!」というスタンスで、支援・指導する側、つまり教職員の関係づくりをすることが大切という話があった。 参加者の感想からも、「3つの心理空間の活用で、人との関わり方の学習を実践的にできるのはすごいなと思いました。」や「さまざまな支援実践や支援策の具体をお話しいただき勉強になりました。何より岡部先生の子どものことを第一に考えているという想いが伝わってくる内容でした。」など、今回の話から、これからの子どもたちへの支援や周りの子どもたちへの関わり方を考える内容が見られた。 また、後半のグループに分かれての話し合いでは、学校内での支援の様子や具体的な指導方法、また支援が必要な子どもたちへの関わりかたが話された。2回目のグループでの話し合いでは、分散登校が始まった学校の様子や今後の学校生活の中で、どのようなことを進めていくことが必要かなど、参加者の中でも意見交換や参考になる実践が話され、「学校でやってみたい」といった声も聞こえた。
2020年06月12日 理論学習会 6/6理論学習会報告
-
主題 学級づくり 子どもが育つ集団をつくる 講師 清水睦美氏(日本女子大学) 日時 5月13日(水)19時~21時 zoomを用いたオンライン形式で開催 参加人数 26名 今回はzoomを使ってオンラインで学習会を行いました。講演①30分、3,4人のグループで意見交流、講演②30分、3,4人のグループで意見交流、まとめという形で学習会を進めました。 講演①では、そもそも学級集団とは何かについて考えました。たまたま集められた人たちの集団であることを教師は理解していなくてはなりません。多様なニーズが求められる中で、うまくいかない子を取り出して対応するのではなく、うまくいかない子に合わせて教室のかたちを変える。変わるべきはマジョリティの人たちであることを学びました。 講演②では、異なる価値観を持つ人たちがたまたま集まった学級集団の意味や、教師がどのように見とるかについて考えました。多様な考えを各個人が持っているからこそ、問題が起きたときにどう向き合わせ、関係を編み直していくかを考えられるようにすることで、個人としての意思決定を尊重することができると学びました。集団を見とる際には、その集団の特徴を捉えること、力に対しどのような位置関係を結ぼうとしているか、そこから生まれるいじめの構造、学級が民主的な集団として機能できているかを考えることが大切だと学びました。 コロナ禍において社会のなかに排除的な風土が形成されつつあることから、学校現場ではいじめがより起こりやすくなるだろうと考えていたので、気を引き締めなければならないと思いました。参加者の感想には、「教師の方から意図的に、相手の立場に立って物事を考える機会を設けたり、互いに補完し合っていく関係になれるよう働きかけていくことが必要であると感じました。」「子どもたちが同じ価値観をもつ危険性について改めて考えさせられました。」などがありました。教師自身が意識を変えていかなければならないと強く感じた学習会でした。
2020年05月24日 理論学習会 5/13学級づくり学習会報告
-
【2019年度 理論学習会総括】 本年度も「貧困と教育」をテーマに学習会を展開した。昨年度までの学習会で、貧困の中にいる子どもや家庭は人や制度、機関との「つながり」を持つことが難しいということがわかった。これまでは子どもへの支援に焦点をあてていたが、その課題は家庭の中の「大変さ」でもあった。その背景から、家庭を支える方法としてどのような可能性があるのか、また、学校でその機関と家庭をつなげるための知識を教員が持つことが必要なのではないかという視点から、学習会の内容をこれまでの知識と合わせ、より視野を広げる内容を設定した。4年間にわたり「貧困と教育」をテーマにしてきたが、今年度は理論としての「貧困」を捉える学習会とともに、「つながり」を意識した子ども達同士の関わり合いをつくる実践報告の形式で学習会を行った。 教育現場の今を見据える力を養うことは重要であると考え、前半の学習会では、大学講師を招いての学級集団を構造的に捉えるための学習会、授業研究会との共同開催で行った小・中学校での子どもたちの「つながり」を意識した授業の実践報告会、産休・育休・働くママパパのための学習会と共同開催したスクールソーシャルワーカーを講師に招いた学習会を開催した。目の前にいる子どもたちやその家庭に対し、教育現場からできる支援を知ることができた。これらの学習会で見えてきたことは、教員が声にならない子どもたちの声を聞こうとすることだった。そして、教員ができることは、排除される、取りこぼされようとする子どもたちが、学校の中で「人とのつながり」をつくるこということだった。 後半の学習会では、若者の奨学金問題を支援する弁護士の活動や、国の制度である社会保障にその枠を広げ、「制度や機関とつなげる」知識をつけるための内容を展開した。昨年度は生活保護に焦点を当てた学習会を設定したが、今年度は生活保護に限定しない社会保障制度について知ることや、奨学金についても取り上げた。貧困の中にいる子どもたちには「学費」も大きな壁となる。義務教育を終え、社会に出ていく子どもたちに、貧困に立ち向かう力の育成、支援の手を持つための「つながり」をつくることが貧困の連鎖を断ち切る術のひとつであることも学ぶことができた。 今年度の学習会を進めていく中で、私たち教員がつけた知識を教育現場でどのように実践していけるのかという課題も見えた。実践していくためには、社会保障・生活保護・奨学金制度の問題など社会の今を捉え続け、子どもが貧困に立ち向かうためにつける力を考えていく必要がある。また、子どもやその家庭に寄り添いながら制度や機関と「つながり」をつくることもそのひとつであるということがわかった。 【活動代表】馬場有希・根岸知世 【内容・日時・場所】 第1回:4月22日(月) 講演会「学級づくりの基本~教室での教師と子どもの関係~」 講師:清水 睦美氏(日本女子大学 教授) 場所:大和市シリウス603中会議室 第2回:5月13日(月) 授業実践報告会「クラスづくりと国語の授業」(授業研究会との共催) 実践報告:山崎 正氏(小学校教諭)・ 飯田 里沙氏(中学校教諭) 場所:大和市シリウス603中会議室 第3回:6月23日(日) 講演「SSWの視点から考える学びの環境づくり~組織的な取り組みの可能性~」(ママパパのための学習会と共催) 講師:上原 樹氏(大和市青少年相談室SSW) 場所:大和市シリウス612文化創造室・会議室 第4回:7月1日(月) 実践報告「題材から授業をつくる」(授業研究会との共同開催) 授業実践報告:馬場有希氏(小学校教諭) 場所:大和市シリウス608和室 第5回:9月2日(月) 文献講読会 テーマ:『性の多様性を考える』 場所:大和市シリウス603中会議室 第6回:10月7日(月) 講演会「奨学金問題からみえる子どもたちの学びの現状」 講師:田原 恵氏(神奈川県弁護士会 弁護士) 場所:大和市シリウス603中会議室 第7回:11月11日(月) 講演会「生活保護から社会保障制度を考える~今とこれからをどう生きるか~」 講師:今井 伸氏(十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 教授) 場所:大和市シリウス603中会議室 (全7回。のべ参加人数61名)
2020年02月25日 理論学習会 2019年度理論学習会総括