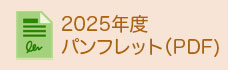-
講演会「学級集団のとらえ方」 ~いじめ問題をどうとらえるか~ 講 師 :清水 睦美 氏(日本女子大学) 日 時:2016年4月18日(月)19:15~21:00 場 所:冨士見文化会館 202号室 (大和駅徒歩 1分) 参加者:10名 『「学級集団のとらえ方」 ーいじめ問題をどうとらえるかー』というテーマで、清水睦美氏(日本女子大学)に講演をしていただきました。「いじめ」の構造が変化してきており、1980年代頃とくらべ、最近では「いじめ」が見えにくくなっている現状があるという話から、現在の「いじめ」がどういう構造から成り立っているのか、「いじめ」が発見される時・繰り返される時にはどのような構造になっているのかを具体的事例を交え、講演していただきました。 また、「いじめ」が深刻であればあるほど見えにくくなること、そして、教師が作り出す雰囲気でその深刻な「いじめ」を生み出しやすくも、生み出しにくくもなるということもわかりました。清水先生の講演を聞き、教師が学級集団をどうとらえるか、その教師自身の価値観が問われるという話からも学級指導をどう進めていくべきか考えさせられました。 「いじめる子」「いじめられる子」という関係だけではなく、それらを取りまく学級集団がどう構成され、教師がどういう雰囲気をもって動いていくのかという課題が見え、今後の学級集団づくりを見つめなおす機会を得られた学習会となりました。 〈参加者感想〉 小集団の形成といじめとの関わりを学んで、強者を一元化しないこと長期的な小ボスにしないことを意識していかなければならないと学びました。今のクラスでも同じ子ばかり中心なので、小グループを壊すことをやっていきたいと思いました。(小学校教諭) フラットな関係というお話がありましたが、本当にそうなのか、その背景は何なのか、先生の見解を聞きたいです。現場では、より関係性に敏感になっているのではないかと思う場面があるからです。フラットならば、多様性は受け入れられるのでは?と思いますが、学校は個々のニーズに応えるという側面が強く受け入れるというより、対応するという受け身の姿勢が強いように思います。(小学校教諭) いじめの構造についてとても分かりやすく説明していただき、勉強になりました。資料のデータをとても興味深く見させていただきました。集団で起こったこと(どの立場の子が加害者になっているかなど)自分自身の指導について見直すことができるということが分かり、これから学級経営をしていく中で今日勉強したことをいかしていきたいと思いました。 学級経営をがんばりたいと改めて思いました。ありがとうございました。(中学校教諭) いじめ衝動とヴァルネラヴィリティのバランスの取り方についてとても分かりやすかった。力から自立しようとしている子たちをどう活かすか、まとまろうとする力が強くなりすぎない、崩していくことが大切なんだと強く思いました。ありがとうございました。(中学校教諭)
2016年05月01日 理論学習会 4月 理論学習会 報告
-
2016年01月27日 理論学習会 1月 理論学習会報告
-
テーマ:『ヘイトスピーチ』から考える人権 報告者:馬場有希(上和田小学校) 村本綾 (つきみ野中学校) 参考文献:『ヘイトスピー「愛国者」たちの憎悪と暴力』安田浩一 文春新書 日 時:2015年12月7日(月) 受付19:00 開始19:15 終了21:00 場 所:冨士見文化会館 参加人数:11人 学習会では、参考文献の章ごとの要約とその章と本書全体の中の気づき・疑問・考えを担当者が発表した。その後の話し合いでは、ヘイトスピーチが過激になり無意識のうちに取り込まれる人が増える要因に、日本の消費社会の影響が挙げられた。このような現状の中でヘイトに取り込まれないようにするにはどうしたらよいのかという答えにはなかなか至らなかった。また、ヘイトの背景には日本人が日本全体が小さくなっていることを受け入れられない状況があるのではという考えが挙げられた。このように、弱者側が権力を乗り越えようとし、立場が逆転しようとする時に、人は力で押しつぶそうとし、それが差別やいじめにつながるという意見が出された。話し合いの最後には、ヘイトスピーチは民族に対する憎悪であって、私たちの生活には容易に入り込むような思想ではないという意見も出された。一方では生活の中の小さな差別意識がいずれヘイトにつながるという意見も出され、この2つの相反する意見交換により、様々な視点で考えることができたように感じる。
2015年12月23日 理論学習会 12月 理論学習会報告
-
2015年11月30日 理論学習会 合同理論学習会(第2回)の報告
-
2015年11月10日 理論学習会 11月 理論学習会報告
-
「労働教育」合同理論学習会(第1回)の報告 2015年10月20日、鍛冶邦彦氏(県中央地域連合事務局長)から「学校教育につなげる労働をめぐるルール」と題する講演をいただきました。 Ed.ベンチャーで支援する外国人青年の「ブラックな」働き方をきっかけとして、「ワーキングプア」「ブラック企業」「老後破産」等の社会問題と、学校や教師はどのように向き合うことができるのかを検討したいという目的から組まれた2回連続講座の学習会は、今回が第1回目です。 講演内容は、鍛冶氏が数年前まで学校教員であったいう背景もあり、私たちの予想をはるかにこえる内容のものでした。「キャリア教育」から始まる「働く」ことに関わる教育が、その一部において「労働教育」に向かおうとしている社会的背景。学校教育の中で扱われる「働く」に隣接する内容(たとえば、勤労、労働、奉仕)の概説。労働と社会保障(セーフティネット)の関係、労働基準法の射程。最後には、社会問題化するような「労働」状態が生み出される社会構造の問題にも触れていただきました。 最後の社会構造の問題は、2016年2月の教育講演会でお招きする平川克美氏の著作『グローバリズムという病』で取り上げられている内容とも関連するものであり、階層化、格差化する社会の中で、「学校がどうあるべきか」「学校教育の内容は、どのように選択されるべきか」を考える1つの柱として「労働」をめぐる問題群を捉える重要性を再確認できました。また、鍛冶氏からは、「子どもたちに何を教えるのかも重要だが、同世代で他の仕事をしている人たちとも連帯していくことはもっと重要」というメッセージも付け加えられました。 今回の学習会は、県中央地域連合との合同企画のため、教員以外の方の参加もあり、懇親会では、異業種の方からさらに突っ込んだお話をお聞きすることができました(参加者22名、懇親会参加者11名)。次回は11月24日(火)で、嶋崎弁護士による「ブラック企業の実態と対処法」の講演です。(SM)
2015年10月29日 理論学習会 合同理論学習会(第1回)の報告
-
2015年10月18日 理論学習会 10月 理論学習会の報告
-
2015年10月10日 理論学習会 9月 理論学習会の報告
-
2015年09月11日 理論学習会 8月 理論学習会の報告
-
2015年07月16日 理論学習会 7月 理論学習会報告