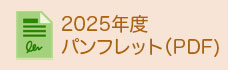-
★案内★8/4学習会開催 外国人の子ども理解のための学習会では、8月4日(月)に下記要領にて学習会を開催いたします。ぜひご参加ください。 日時:8月4日(月)13:00~16:00 場所:大和市シリウス612(文化創造室) 内容:外国人の子どもが置かれている状況を考える~映画『はざま-母語のための場所を探して』を通して (映画上映と講師による対談及び参加者とのディスカッション) 講師:映画監督 朴基浩(ぱく きほ)氏 日本女子大学教授 清水睦美氏 8/4外国人の子ども理解学習会チラシダウンロード 外国人理解のための学習会では、これまで外国人の子どもたちが置かれている状況等をテーマに取り上げてきました。 今回は、「日本と出身国を往来する移民の子ども社会統合を見据えた言語教育―母語・公用語の補習教室を地域の「多文化共生」の拠点にプロジェクト」制作のドキュメンタリー映画『はざまー母語のための場所を探して』を上映します。 映画上映の後、講師の清水氏による課題の整理を受けて、映画製作監督の朴喜浩氏と清水氏との対談、さらに参加者とのディスカッションを通して、日本における移民をめぐる問題や多文化共生について考えます。 参加を希望される方は、学習会担当西岡(ayumin31@gmail.com)までお申し込みください。 ※お預かりした個人情報は学習会に関するご連絡以外には使用いたしません。 お知り合いの先生で、外国人の子どもの支援に関心を持たれている方がいらっしゃいましたら、事例研究会の開催についてご紹介いただけますようお願いいたします。 多くの方の参加をお待ちしています。
学校支援活動
-
うれしい出来事 【エステレージャ教室 8~9月報告】 9月、エステレージャにうれしい出来事がありました。 中学生のSさんが書いた平和に関する作文が、学校代表の作文の1つに選ばれ、新聞に掲載されたのです。教室では、帰りの会でSさんに作文を披露してもらい、スタッフも作文を聞いた子どもたちもSさんの努力を讃えました。 Sさんは、小学校2年生からエステレージャに通っている子どもです。作文が苦手で、作文の宿題があると教室に持ってきて、スタッフと一緒に作文に取り組んでいました。小学校2年生の時には、「作文をどうやって書いたらいいか分からない。でも、先生が『1年生の時に教えたから教えません。』と言ったから・・・書けない。どうしよう。」と話していたことがあります。外国人の子どもにとって、作文はとてもハードルが高い学習活動で、日本語を上手に話せていても、作文が書けないことはよくあることなのに、一度教えたから教えないというのは・・・とスタッフの話題になったことが思い出されました。 Sさんの作文が、私たちスタッフに2つのことを教えてくれました。1つは、継続することが力になっていくということです。Sさんは作文を書くときには、いつもスタッフと話をしながら、自分の経験や意見、考えを話し、それを作文に書いていくということを続けてきました。作文は苦手で面倒だけれども、課題にまじめに取り組んできました。あきらめず続けていくことで、力がついてくるということをSさんの作文が教えてくれました。 もう1つは、自分の意見や考えを言葉にする力を育てることの大切さです。Sさんが平和の作文に取り組んでいた時、中学校2年生のKさんも人権作文に取り組んでいました。Sさんと同じように、スタッフはKさんの経験や考えを聞きながら進めていきました。人権という言葉を確認した後、人権が守られているあるいは侵されていると感じることはないか、それに対してどんなことを感じるか、考えているかなど、まずKさんの経験や考えを聞こうとしました。しかし、Kさんからは言葉が出てきませんでした。人権というテーマは難しいテーマで、大人でも作文を書くのが難しいので、どんな言葉でもいいから考えていること、思っていることを自分の言葉で話してほしいと思いました。しかし、Kさんから言葉が出てこなかったため、作文が書けないまま終わってしまったということがありました。この時、対応していたスタッフはKさんが自分の考えや意見を言葉にできないことを残念に思いました。Kさんも低学年から教室に通ってきている子どもで、小学生の時には不平不満も含めて学校であったことをよく話してくれていました。しかし、自分の言葉で考えや意見を表明することができなかったのです。Kさんの作文を支援している中で、事実を伝えるだけではなく、思いや考え、意見を持つこと、そしてそれを表明する言葉が持てるように支援することが必要だと感じました。 Sさんの作文は、学習を支援することはもちろん必要ですが、自分の意見や考えを持ち、それを表明する言葉が持てるような支援をすることが必要であるということも教えてくれました。Sさんの作文は、エステレージャが目指すべき課題も教えてくれました。
外国人支援・こども支援活動
-
No.69教育の役割とは Ed.ベンだよりNo.69が発行されました。 今回のEd.ベンだよりのタイトルは「教育の役割を『現代』という時代の中で模索するⅡ」です。 Ed.ベン便りNo.69ダウンロード 今回のEd.ベン便りでは、前号(No.68)に引き続いて、「教育の役割とは何か」について考えていきます。特に今回は「学校離れと格差の固定化」に焦点が絞られています。 私が学生の頃、ゼミで教育の成果とは何かということについて、ああでもないこうでもないと延々と議論したことを思い出します。結局その時は結論は出なかったのですが、私の師が「教育はボクシングのボディーブローみたいなものだ」と呟いた一言を今でもはっきりと覚えています。 「教育の成果なんてものは、ストレートやアッパーカットのようにすぐに相手を倒すように短期的に現れるものじゃない。それは地味なボディーブローがジワジワと相手の体力と脚を奪って、後から効いてくるように、長い時間をかけて社会に影響を与えるものだ」と。だからこそ子ども時代の経験が大事なのだ、というようなことを仰っていました。その議論の中では「学力」という言葉はさほど重視されていなかったように思います。だからこそ、学力テストが始まったころからの「まず学力ありき」の風潮に、頭の中の隅っこにいつも「?」が浮かんでいます。 「教育の役割とは何か?」「教育とは何か?」という根本的な問題について、ぜひ今回のEd.ベン便りを参考に考えてみたり議論してみてはいかがでしょうか? また、8月中までに開催されるEd.ベンチャーの研究会、学習会、スタディツアーの案内も掲載されています。みなさま是非ご参加ください。
Ed.ベンだよりPDF
-
2025年07月17日 外国人の子ども理解の学習会 ★案内★8/4学習会開催
-
外国人の子ども理解の学習会では、事例研究会を下記の要領で開催いたします。 日時:7月26日(土)13:30~15:30 場所:オンライン開催(Zoom) 事例:「これまで出会った学習者~20年を振り返って」(報告:日本語指導員) 20年間の日本語指導を通して出会った学習者や保護者等の様子や変化などについての報告を受け、子どもたちが抱えている困り感がどのように変わってきているのか、今、支援者に求められていることは何かを考えていきたいと思います。 参加を希望される方は、担当の篠原(h-sunflower@jcom.home.ne.jp)までメールでお申し込みください。資料とZoomのID,パスコードを後日お送りします。 ※お預かりした個人情報は学習会に関するご連絡以外には使用いたしません。 お知り合いの先生で、外国人の子どもの支援に関心を持たれている方がいらっしゃいましたら、事例研究会の開催についてご紹介いただけますようお願いいたします。
2025年07月17日 外国人の子ども理解の学習会 案内★7/26事例研究会開催
-
2025年07月11日 Ed.ベン便り No.69教育の役割とは
-
2025年06月09日 お薦めの書籍・文献 ガザ日記:ジェノサイドの記録
-
2025年06月05日 Ed.ベン便り No.68教育の役割を模索する
-
2025年05月15日 お薦めの書籍・文献 この計画はひみつです
-
授業研究会報告:第1回(3月29日) 参加者11名(対面のみ) 2025年度の授業研究会の一つの柱は、東京一極集中を促してきた高度経済成長の背後の資本主義に焦点をあてつつ、東京と地方の教育にどのような格差を生みだしてきたのか、また、その格差を解消するための道筋として、どのようなことを考えればいいのかを検討するということです。 今回は卒業論文で「脱資本主義の思想としての地方移住の可能性を考える-教育観や子育てに対する考え方に焦点を当てて-」に取り組んだ門井みなみさんに報告をお願いし、それをもとに検討を行いました。 論文に対しては、現在の学校教育が資本主義の担い手育成の装置になっていることを明言しており共感がもてた。また、地方移住に資本主義からの逃れる可能性を見出している人々がいるものの、そこで新たな価値観に出会うのではなく、再び子育ての中で資本主義に絡めとられていくことへの葛藤が見受けられることも興味深かった、という感想があがりました。 他方、今回の論文検討を通して、次の課題を検討する必要が共有されました。 ①地方に都市部とは違った価値観を見出しているとすれば、それは何であるのか、そこに学校教育を絡んでいくことができるのか。 ②人間の権利に対する考え方の浸透は、外国人労働者の処遇などの問題は見れば、地方より都市部の方が進んでいるように見えるが、この問題をどのように考えていくのか。 ③地方の中に入り込んで、都市部の資本主義とは異なる社会経済活動を構築する動きがあるとすれば、そのような具体的な事例があるのか。 以上の課題は、今後の研究会の中で深めていくことになりました。
2025年05月06日 授業研究会 【報告】3/29授業研究会
-
学習会報告 日時:2025年3月29日(土) 10:30~12:00 参加者:11名 内容:「参加者それぞれの現場から排除の実態を報告し合い、現状を認識する」 今回の学習会では、小学校、中学校で見られる”インクルーシブでない状態”について語り合いました。 国際級在籍の生徒に対して試験問題にルビを振らない教員がいる。以前ほど教員が家庭訪問を積極的に行わなくなった。我が子の人間関係に過敏な保護者に対して毅然とした態度を示せないなど、様々な苦しさを抱える子どもに対して、出来ないことを学校・教員の責任を子どもに押し付けてしまっている現状。また、教室で子ども同士が多様性を認知し、受け入れるまでにかかる時間を学校が確保しづらくなっている現状が指摘されました。学校に通う子ども以上に、教職員集団や保護者の意識についても話題が及ぶ有意義な時間となりました。 今回確認された現状を踏まえ、参加者各々がどのように子ども、そして職員集団・学校現場の抱える課題と向き合っていくのか。8月の学習会に向けて考えていきたいと思います。 【参加者の感想より】 ・保護者としてと特別支援の方が手厚いからという感覚、すごく分かります。「インクルーシブにするよ」「学級を20人にするよ」が実現したらいいな..と思います。インクルーシブの理念と政策のズレが矛盾がすごく感じられて、意味のないことをどんどん進めているんだなと思いました…。クラス替えが1年ごとなのはリスク回避になるということをはじめて知り、年度替わりに毎年不安定になる子どもたちを考えると、本当に大人のためのクラス替えなんだなと思いました。 ・最近、教育と労働の関りに関する議論をした。剰余価値を増やすためには、2つのパターンがあるという。1つは単純に労働時間を増やすということ、もう1つは短時間でより多くの価値を創出可能な労働者を使役すること。教育は後者に関わっているという。今日の議論をきいていると、現状の教育は効率的な生産者を産み出すことに焦点化した教育の形に近づいているように感じる。その一方で、必ずしも教育現場で行われていることが効率的な生産者の生産に寄与するわけではないだろう。インクルーシブ教育もその一つである。インクルーシブ教育は基本的に生産性を高めることに直結するわけではない。生産性と関連の低い教育活動の価値を再確認するべきだと考える。 ・学校がインクルーシブになることには、教師意識だけでなはなく保護者の意識や制度的なものなど、様々なハードルがあることを理解しました。インクルーシブをすすめることは、とても難しく思うようにいかないのだろうと思います。「(多様性の認知・受容に基づくインクルーシブの実現には)時間とお金がかかる」という言葉が印象的でした。効率を重視する学校の中で、子どもたちがますます生きづらくなっていくのが予想されるだろうなと思うとやりきれないです。 ・東京、日本だとその子に合わせた分離することをインクルーシブと言っている現状がある中で、「インクルーシブ」というものを話すことがまず大事なのだなと思った。 ・自分の学校でいかにインクルーシブの考えが実践されていないかを痛感しました。また、この1年で自分が日本の学校教育の悪いところにとりこまれて、大切な考えが失われていたことにも気付きました。 ・学校現場での「インクルーシブではない実態」が報告され、とても参考になった。学校の教室そのものが持つ理念が、インクルーシブから離れてしまっていることがよくわかった。 ・インクルーシブな社会を目指すには、自分も学校の中で考えを戦わせたり、もっと理解を深める取り組みが必要で、まだまだフォローしきれていない子どもがたくさんいると感じた。 ・何のために学校があるのか、教室をどんな場所として位置づけるのか、改めて、突き詰めて考えていかなければと思いました。担任をしていた頃、学級目標を温かいクラスとして、運動会や合唱コンでは、力を入れずにのんびりと学級経営をしていましたが、今は難しいのですかね。 ・子どもと生活していく中で、自分のした行動、言葉掛けで子ども同士の関係性が分断されたと感じる場面があり、あのときの反省を振り返ることができました。「子ども主体に」と言われ続ける教育現場で、子どもを誘導する教師の責任は問われず、何かあったら子どもの責任、問題を子どもに求めている実態があることを認識して、違和を行動や言語化して伝えていくことを目標に教育に向き合っていきます。 ・子ども、教室のインクルーシブの前に職員間のインクルーシブを実現する必要性を感じる。意見を交換するための時間、また教育観・価値観をすり合わせることにもっと時間をかけたい。特に、若手とベテラン、20代と50・60代の教職員の乖離をつなぎ留めたいと思っています。
2025年04月15日 インクルーシブ社会を目指す学習会 【報告】3/29学習会
-
Ed.ベンだよりNo.67が発行されました。 今回のEd.ベンだよりのタイトルは「2025年度定期総会と教育講演会の報告」です。 Ed.ベンだよりNo.67ダウンロード 去る2月16日にEd.ベンチャーの定期総会が開催されました。また同日午後には、「核政策を知りたい広島若者有権者の会( カクワカ広島)」の共同代表である田中美穂さんを講師としてお招きし、「今の世界の現実を自分事として未来に向けて受け止める」というテーマで講演会とパネルディスカッションを開催しました。 今回のEd.ベンだよりは新年度にあたっての会長挨拶と教育講演会の要約が掲載されております。 昨年度の総会及び教育講演会の折にも、世界のいたるところで激しい戦争が行われ、多くの人々が傷つき尊い命が失われていました。今年になってもそれらは収まる気配が見えず、益々混沌の度合いを深めているようにも見受けられます。遠くの国の戦争だから関係ない、と思うのではなく、「平和」ということについて、自分のこととして考えていく必要がどんどん重要になってきているように思います。ぜひ今回のEd.ベンだよりをお読みください。 また、5月までのEd.ベンチャーの学習会の案内も掲載しております。みなさまのご参加をお待ちしております。
2025年03月18日 Ed.ベン便り No.67総会・講演会報告
-
Ed.ベンだよりNo.66が発行されました。 今回のEd.ベンだよりのタイトルは「若い先生方に是非とも考えてもらいたい問題」です。 Ed.ベンだよりNo.66ダウンロード 早くも新しい大統領の言動に世界が振り回されています。太平洋を渡ったはるかかなたの国のことだから、私たちには関係ないと思いがちですが、グローバルな時代ですから、やはりいろいろなこと、とりわけ政治経済面では大きな影響が出てきそうです。学校や教育のことは、政治や経済のこととはちょっと距離がある、と思われるかもしれませんが、決してそんなことはないと思います。 直接すぐに影響があることではないとしても、やはりこのところの世の中の動きには注意して目を配っておく必要があると思います。今回のEd.ベンだよりの内容を手掛かりとしていただければと思います。 また、2月16日に開催予定の2025年度教育講演会についてもお知らせが掲載されています。今回は「核政策を知りたい広島若者有権者の会 共同代表の田中美穂氏においでいただき「平和」について議論を交わしたいと思います。こちらにもぜひご参加ください。 さらに3月29日開催される予定の総合学習会に関するお知らせも掲載されています。午前中はインクルーシブな社会を目指す学習会、午後には外国人の子ども理解のための学習会、そして夕方からは授業研究会が行われます。関心のある学習会だけの参加でも結構ですし、一日中の参加でも結構です。ぜひご参加ください。
2025年02月05日 Ed.ベン便り No.66若い人たちに考えてほしいこと
-
日時:2024年12月6日(金) 19:30~21:00 内容:「子どもアドボカシーを知っていますか~子どもの声を聴く意味 そして私たち一人ひとりができること~」実践報告 講師:相澤京美氏(NPO法人子どもアドボカシーを進める会 TOKYO) 参加者:4名 今回は、5月に行った子どもアドボカシーについての学習会で、講師の相澤氏からのお話を伺ってそれぞれの場所と立場で実践したことの報告を行いました。そして、実践報告に対して改めて相澤氏からもお話を伺いました。 中学校での実践では、中学2年の道徳の授業で「子どもの権利条約」を題材とした実践が報告されました。人権という言葉自体が子どもにとってなじみの薄いものであることもあり、「虐待」や「戦争」といった状況に置かれた子どもを守るための限定的なものとして理解されている様子が見られました。ただ、「子どもの権利条約」の条文を見る中で、家族との関係や日々の生活の中で疑問に思っていることを話題に挙げる生徒もおり、「人権」という言葉を身近なものと捉え直す様子も見られました。一度きりの授業であったため、生徒はアドボカシーにおいて重要な「意思表明権」、そして「子ども自身に権利がある」ということを知るだけで終わってしまいましたが、3年では公民の授業も始まるため、今回1回の授業で終わることなく、次の授業に繋げていきたいと思いました。授業でできることには限界があることも共有し、日常の中で「これがあなたの権利だよ」と伝えて浸透させていくことが大事と、相澤氏からお話をいただきました。 児童養護施設での実践では、県のアドボカシー事業の方々が来園したときの子どもたちの反応や、「まず子どもの考えを聴くこと」を意識した中で、できたこととできなかったことについての報告となりました。これまで分からなかった子どもの考えを知ることができたこと、子どもが話せば話すほど混乱していったり、できない現実にぶつかったりと、そのフォローの難しさや時間の足りなさ、その中での変化も感じたこと、などの話が挙がりました。相澤氏からは、施設が子どもアドボカシーを実践していくことが一番難しいこと、施設で「助けて」と言える関係性が作れると良いこと、などのお話をいただきました。 相澤氏からは、歴史的な観点からも権利は圧に対するものとして生まれた概念で、大人への抵抗ということ、それを現在の学校現場でフォーマルアドボカシーという立場で実践していくことには限界があるが、意見をいつでも聞くよという姿勢を見せておくことが大事とのお話、学校でアドボカシー事業を取り入れている事例も増えているとのお話もありました。今も、これからも、子どもたちと接しているすべての大人が、子どもの権利について考えていくこと、権利を尊重していくことを怠らないこと、そしてその考えを浸透させていくことが必要で、わたしたちに与えられている課題であると感じました。
2025年01月05日 インクルーシブ社会を目指す学習会 【報告】12/6学習会
-
この度、兵庫県神戸市を中心に外国人支援の活動を行っている神戸定住外国人支援センター様より、定住外国人の子どもたちを支援するための奨学金クラウドファンディングに関するお知らせをいただきました。 このクラウドファンディングを行っている「定住外国人子ども奨学金実行委員会」は、外国にルーツを持ち、兵庫県に住む、経済的に困難な環境にある子どもたちの高校入学・高校生活を支援しています。 また、奨学金の支給にとどまらず、奨学生との対話を通じて3年間の高校生活を見守り、卒業できるように、また卒業後のさらなる飛躍を見越して、必要な伴走支援を行っています。 今回のクラウドファンディングを機に、財政を改善するとともに、 さらに多くの方々に外国人生徒の現状と奨学金について広く知っていただきたいとのことです。 このクラウドファンディングの詳細や寄付の方法については、下記のリンクをご覧ください。 https://congrant.com/project/kfcscholarship/13731 ご興味のおありの方は、是非ご覧いただき、参加等についてご検討いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
2024年12月20日 お知らせ KFCのクラウドファンディングについて
小学校のふりかえり https://t.co/uY9bmkbKPs
— Ed.ベンチャー (@edventrue) May 14, 2023